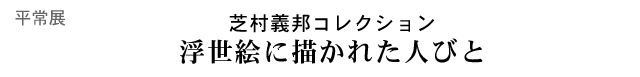| 企画展示室1 |
| 番号 |
作家名 |
作品名 |
年代 |
| 314 |
┐歌川国芳 |
出雲屋お國(いずもやおくに) |
|
| 315 |
│ |
不破伴左ヱ門重勝 (ふわばんざえもんしげかつ) |
|
| 316 |
┘ |
名古屋山三元春(なごやさんぞうもとはる) |
|
| 322 |
┐歌川国芳 |
岩藤召仕おちよ(いわふじめしつかい) |
|
| 321 |
│ |
若党 之清(わかとうばくちこれきよ) 之清(わかとうばくちこれきよ) |
|
| 320 |
┘ |
尾上召仕お初(おのえめしつかいおはつ) |
|
| 349 |
歌川国芳 |
稚立武勇揃(おさなだちぶゆうぞろい) |
|
| 327 |
歌川国芳 |
中納言氏定実ハ石川五右衛門
(ちゅうなごんうじさだじつはいしかわごえもん) |
|
| 326 |
┐歌川国芳 |
此下藤吉 奥方綾の臺(このしたとうきち おくがたのだい) |
|
| 330 |
┘歌川国芳 |
見立十二支之内 午(みたてじゅうにしのうち うま) |
|
| 331 |
歌川国芳 |
見立十二支之内 未 河古屋 岩永宗連
(みたてじゅうにしのうち ひつじ かわこや いわながしゅうれん) |
|
| 334 |
歌川国芳 |
江都錦今様國盡 一休禅師 地獄太夫 児雷也 越中 越後
(えどにしきいまようくにづくし いっきゅうぜんじ じごくたゆう じらいや
えっちゅう えちご) |
|
| 335 |
歌川国芳 |
江都錦今様國盡 白井権八 塩谷判官 因幡 伯耆
(えどにしきいまようくにづくし しらいごごんぱち しおやはんがん いなば
ほうき) |
|
| 370 |
歌川国芳 |
墨戦之図
(ぼくせんのず) |
|
| 360 |
歌川国芳 |
文月(ふみづき) |
|
| 373 |
歌川国芳 |
浮世又平名画奇特(うきよえまたべえめいがきとく) |
|
| 338 |
歌川国芳 |
市村羽左衛門(いちむらうざえもん) |
|
| 339 |
歌川国芳 |
雪姫(ゆきひめ) |
|
| 354 |
歌川国芳 |
燿武八景 石山暮雪(ようぶはっけい いしやまぼせつ) |
|
| 355 |
歌川国芳 |
燿武八景 東大寺晩鐘(ようぶはっけい とうだいじばんしょう) |
|
| 356 |
歌川国芳 |
燿武八景 堀川晴嵐(ようぶはっけい ほりかわせいらん) |
|
| 534 |
二代
歌川国輝 |
一力長五郎(いちりきちょうごろう) |
慶応3年
(1867) |
| 536 |
二代
歌川国輝 |
小柳常吉(こやなぎつねきち) |
元治元年
(1864) |
| 538 |
二代
歌川国輝 |
増位山大四郎(ますいやまだいしろう) |
慶応年間 |
| 540 |
二代
歌川国輝 |
武者ヶ崎倉吉(むしゃがざきくらきち) |
慶応年間 |
| 542 |
二代
歌川国輝 |
象ヶ鼻平助(ぞうがはなへいすけ) |
安政4年
(1857) |
| 544 |
二代
歌川国輝 |
両国梶之助(りょうごくかじのすけ) |
元治元年(1864) |
| 546 |
二代
歌川国輝 |
荒馬大五郎(あらうまだいごろう) |
慶応2年
(1866) |
| 548 |
二代
歌川国輝 |
雷電震右ヱ門(らいでんしんえもん) |
慶応2年
(1866) |
| 551 |
二代
歌川国輝 |
高見山大五郎(たかみやまだいごろう) |
慶応2年
(1866) |
| 553 |
二代
歌川国輝 |
堺川浪右ヱ門(さかいがわなみえもん) |
慶応2年
(1866) |
| 555 |
二代
歌川国輝 |
達ヶ関森右ヱ門(たつがせきもりえもん) |
元治元年
(1864) |
| 557 |
二代
歌川国輝 |
兜山和助(かぶとやまわすけ) |
元治元年
(1864) |
| 559 |
二代
歌川国輝 |
鬼ヶ崎網之助(おにがざきつなのすけ) |
慶応2年
(1866) |
| 561 |
二代
歌川国輝 |
小柳春吉(こやなぎはるきち) |
慶応2年
(1866) |
| 563 |
二代
歌川国輝 |
大纒長吉(おおまといちょうきち) |
元治元年
(1864) |
| 565 |
二代
歌川国輝 |
綾瀬川山左ヱ門(あやせがわさんざえもん) |
明治2年
(1869) |